ホーム > 請願・陳情 > 安城市議会請願書及び陳情書取扱要綱
請願書及び陳情書の取扱いについては、法令又は規則の定めがある場合を除くほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 請願は、必ず文書によること。
(2) 請願書は、邦文を用いること。
(3) 請願書は、請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所を記載し、請願者が署名又は記名押印をするとともに、表紙には請願書と明記すること。
(4) 法人の場合は、その所在地、名称を記載し、代表者が署名又は記名押印をすること。
(5) 請願者多数の場合は、代表者を定めること。定めのない場合は、その筆頭者を代表者とみなす。
(6) 法人でない団体にあっては、代表者の氏名で請願するものとする。
(7) 請願書において内容が数項目にわたる場合は、なるべく別書きにすること。
(8) 請願書は、議長あてに提出すること。
(1) 請願書を提出するには、議員の紹介を必要とする。
(2) 請願の紹介については、正副議長及び所管の正副委員長は紹介議員になることを自粛する。
(3) 紹介議員は、請願書の表紙に署名又は記名押印をすること。
(4) 紹介議員は、その請願が委員会で審査されるときは、委員会の要求に応じて説明しなければならない。
(5) 紹介議員の紹介取消しについて、次のようにする。
ア 受理後議会の議題にされる以前のものについては、議長の許可を得て取り消すことができる。
イ 受理後議会の議題にされたものについては、議会の意思決定前に限り、議会の許可を得て取り消すことができる。
(6) 議会の議題とされた後に、紹介議員の死亡若しくは辞職又は紹介議員の取消しにより紹介議員がいなくなった場合、請願書は引き続き請願として取り扱う。
(1) 請願書は、議長において受理する。
(2) 定例会招集前の議会運営委員会の開催日前3日まで(安城市の休日を定める条例(平成2年安城市条例第29号)第1条第1項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)に受理した請願書については、当該定例会の会期中に審査し、その後に受理したものについては、原則として次の定例会で審査する。
(1) 受理後議会の議題とされる以前のものについては、議長の許可を得て撤回することができる。
(2) 受理後議会の議題とされたものについては、議会の意思決定前に限り、議会の許可を得て撤回することができる。
(1) 議長は、受理した請願書について請願文書表を作成し、本会議において議員に配布し、所管の常任委員会又は議会運営委員会に付託する。
(2) 常任委員会に係る請願のうち、議長が必要があると認めるものは、議会の議決で特別委員会に付託することができる。
(3) 請願の内容が2以上の常任委員会の所管に属する場合は、2以上の請願が提出されたものとみなし、それぞれの常任委員会に区分し付託する。
(4) 議長は、会議の議題となった請願書の常任委員会又は議会運営委員会への付託を省略することについて、討論を用いずに議会の議決に付して決定することができる。
(1) 委員会は、付託された請願を速やかに審査するものとする。
(2) 請願の審査に当たり、執行機関の意見を聴取することができる。
(3) 委員会で必要と認めたときは、請願の事項について実地調査をすることができる。
(1) 委員会において請願の審査を終了したときは、委員長は、議長に請願審査報告書を提出しなければならない。
(2) 議長は、請願審査報告書を受理したとき、これを本会議に付さなければならない。
(1) 請願書は提出の順に番号を付し、受理簿に記入し、整理する。
(2) 請願番号は、暦年ごとに管理する。
(3) 請願文書表には、受理番号、受理年月日、件名、請願者の住所及び氏名、紹介議員の氏名、請願の要旨並びに付託委員会を記載する。
(4) 請願者数人連署のものは、代表者氏名ほか何人と記載する。
(5) 議長は、本会議の決定を得た請願について、その結果を請願者に通知する。
(6) 会期中の委員会で継続審査となった請願について、委員長は、閉会中も継続審査できるように議長に申立ての手続をする。
(7) 議長は、議会の採択した請願で、市長その他の関係機関に送付しなければならないものはこれを送付し、その処理の経過及び結果の報告を請求することに決したものについては、これを請求する。
請願書の例による(ただし、表紙及び紹介議員の署名を除く。)。
請願書の例による。
請願書の例による。
議長は、提出された陳情書のうち、次の各号に掲げる基準を参酌して会議の議題とする必要がないと認めるものにあっては一般文書扱いとして全議員への配布のみするものとし、議長が会議の議題とする必要があると認めるものにあっては請願書の例により会議の議題とする。なお、会議の議題とする必要があるかを判断するに当たり、議長は議会運営委員会に諮問をすることができる。
(1) 提出に際して、議長のもとに郵送されたもの
(2) 本市に住所又は所在地を有しない者のみから提出されたもの
(3) 陳情の内容において、議長が処理できるもの
(4) 陳情の内容が、本市の権限に関与しない事項に係るものであって、国・県等の施策にその対応が委ねられているもの
(5) 陳情の内容において、個人や団体を誹謗中傷し、又はその名誉をき損するおそれのあるもの
(6) 陳情の内容が、法令違反、違反行為等を求めるもののほか、公の秩序に反するおそれのあるもの
(7) 陳情の内容において、係争中の裁判事件や審査請求等に関するもの
(8) 陳情の内容において、市職員等に対して、懲戒、分限等の処分を求めるもの
(9) 陳情の内容において、趣旨、願意等が不明確で判然としないもの
(10) 陳情の内容において、1年以内に同一内容の趣旨で提出されたもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、議長が会議の議題にすることを要しないと判断するもの
請願書の例による。
請願書の例による。
請願書の例による。
紹介議員に関する部分を除き、請願書の例による。
陳情書の提出について、正副議長及び所管の正副委員長は、陳情書の提出を自粛する。
請願書又は陳情書以外の議長あてに提出された陳情書に類するものであって、要望書等の名称を付した文書は、原則として一般文書扱いとし、請願書及び陳情書の取扱いと区分する。
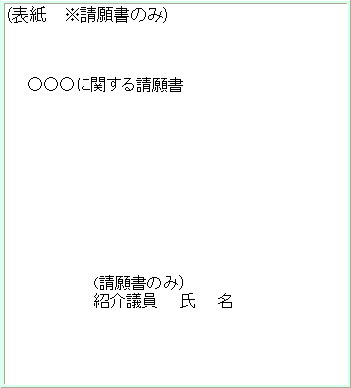
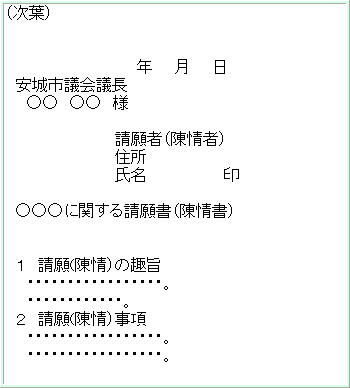
1,個人の場合は、住所を記載し、本人が署名又は記名押印をすること(※本人が署名する場合は押印を省略できます)。
2,法人の場合は、所在地、名称を記載し、代表者が署名又は記名押印をすること。
3,請願者(陳情者)が多数の場合は、代表者を定めること。
4,法人でない団体は、代表者の氏名で請願(陳情)すること。
5,内容が数個にわたる場合は、なるべく別書きすること。